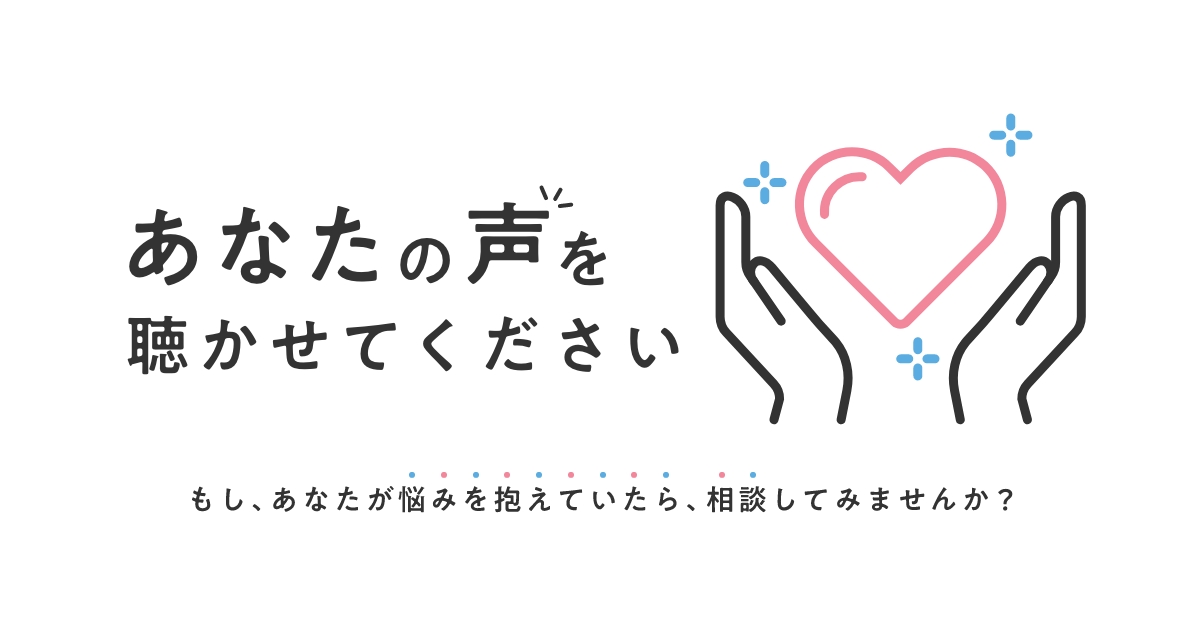こどもの自殺者数が過去最多
令和7年1月29日、厚生労働省が、警察庁の統計に基づき、2024年(令和6年)の自殺者数(暫定値)を公表しました。
令和6年の自殺者数の暫定値は2万268人。これは、昭和53年の統計を開始して以降、2番目に少ない数値となります。
一方、小中高生の自殺者は、令和4年の514人、令和5年には513人を上回り、527人(高校生349人、中学生163人、小学生15人)と過去最多となっています。
これを受けて、令和7年2月10日、文部科学省は、各都道府県教育委員会等に宛てて、生徒の自殺予防に係る取組の強化について通知を出しました。
1人1台端末等を活用した心の健康観察、教育相談体制の構築、校内連携型危機対応チーム・ネットワーク型緊急支援チームの設置等、相談窓口の周知や自殺予防教育の実施等について記しています。
年々、増加するこどもの自殺。
その現状と対策について、まとめました。
※2025年(令和7年)2月20日現在
こどもの自殺の現状
令和6年版「自殺対策白書」におけるこどもの自殺の現状は以下のとおりです。
こどもの自殺の原因と動機
- 小中高生は、自殺の原因・動機が「不詳」である割合が高い。
- 「家庭問題」の割合が高いのは、男女ともに小学生。
- 「健康問題」の割合が高いのは、女子高校生。
- 「学校問題」の割合が高いのは、男性では中学生、高校生。女性では中学生。
自殺未遂歴との関連
- 2022年以降、小中高生は男女ともに、自殺未遂があった時期が自殺の1年以内である場合が過半数。
- 特に女子小学生や女子高校生では、自殺から1か月以内に自殺未遂歴があった自殺者の割合が高い。
こどもの自殺が多い時期
- 2009年以降、8月後半から増加し、特に夏休み明けの9月1日に多くなっている。
- 「北海道・東北地方」については、他の地域よりも自殺の多い時期が1〜2週間早い(夏休み明けが早い)。
国のこどもの自殺対策の流れ
| 令和4年10月 | 第4次「自殺総合対策大綱(子ども・若者の自殺対策を強化)」閣議決定 |
| 令和5年4月〜 | 「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(定期的に開催、対策の進捗状況を確認) |
| 令和5年6月 | 「こどもの自殺対策緊急強化プラン」取りまとめ |
こどもが使えるツール
Webコンテンツ
かくれてしまえばいいのです
生きるのがしんどいと感じている子どもや若者向けのWeb空間です。
匿名・無料で24時間いつでも利用することができます。
相談先を探す
こども家庭庁相談窓口
悩みの内容やフリーワードから、相談できる窓口を知らせてくれます。
内閣府孤独・孤立対策推進室チャットボット
もやもやから抜け出すヒントとなる相談窓口をチャットボットで知らせてくれます。
こども家庭庁「まもろうよ こころ」
電話やSNSでの相談窓口をわかりやすくまとめています。
話す・相談する
チャイルドラインチャット相談
18歳までの人が、相談員と1対1でチャットで話ができます。
BONDプロジェクトLINE相談
10代・20代の生きづらさを抱える女の子のためのLINE相談。
あなたのいばしょチャット相談
24時間365日、誰でも無料・匿名で利用できる相談チャット。
生きづらびっと
「死にたい」「消えたい」といった、つらい気持ちを安心して話せるSNS相談。
こころのほっとチャット
ウェブチャット形式のカウンセリング。
読む・リーフレット
「しんどいって言えない」
国立成育医療研究センターのリーフレット「しんどいって言えない」
自分を傷つけているあなたへ。今できることを一緒に探してみませんか。
こどもに関わる大人が利用できるツール
教職員向け
「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」
文部科学省が、教職員に向けて、こどもの自殺予防のマニュアルとリーフレットを掲載。
「自殺防止対応案内ボード」
東京都保健医療局が、教職員に向けて、こどもの自殺防止のためのリーフレットを作成。
「こころとからだのモヤモヤってなんだろう」
特別支援学校での、こころの健康教育に活用できる自殺対策普及啓発ツール
大人全般に向けて
ゲートキーパーになろう!
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、 話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと。
ゲートキーパーについての研修動画などがあります。
国の機関の取り組み
国の機関での、最近の取り組みの例を挙げてみます。
こども家庭庁の取り組み
高校生を対象にしたワークショップ
高校生を対象に、悩みを持つ友人に対し、自分ができるサポートを考えるワークショップを開催。
保護者等を対象に講演会
保護者等、日常的にこどもに関わる機会が多い人を対象に「こどもの心のサイン」と「望ましい行動と対応」を学ぶ講演会を実施。
インターネット調査
15歳〜59歳を対象に、こどもの自殺に関する認識や取組等の実態について全国的なインターネット調査を用いた調査を実施。
メディア周知
広報施策について、メディアに周知。
文部科学省の取り組み
1人1台端末を利用した「心の健康観察」導入推進
児童や生徒の持つ端末を利用し、メンタルヘルスの悪化や小さなSOSなどを察知し、問題が表面化する前に、未然防止を図るための「心の健康観察」を導入し推進していく。
SNS等を活用した相談体制の構築
若年層が主に用いるコミュニケーション手段であるSNSを活用した相談体制の整備。
内閣府の取り組み
孤独・孤立対策のための相談窓口体制の推進
誰一人支援から取りこぼされない社会に向けて、孤独・孤立対策の相談窓口体制を推進。地方公共団体やNPO法人への交付金や活動事例の周知。
「つながりサポーター」養成
できる範囲で困っている人を助ける一般市民の「つながりサポーター」の養成。
厚生労働省の取り組み
こども・若者の自殺危機対応チーム事業
学校と地域が連携して、児童生徒等の自殺を防ぐための新たな取り組みとして「こども・若者の自殺対応チーム事業」を、全国で展開することを目指す。
長野県で先行モデル事業として実施している。
まとめ
近年増えつつあるこどもの自殺について、現状と対策についてまとめました。
とても胸の痛む話で、こどもに関わる大人にとっても難しい課題です。
本記事が、現状やその背景と向き合い、自分の立場でできることを考えるきっかけになれば幸いです。