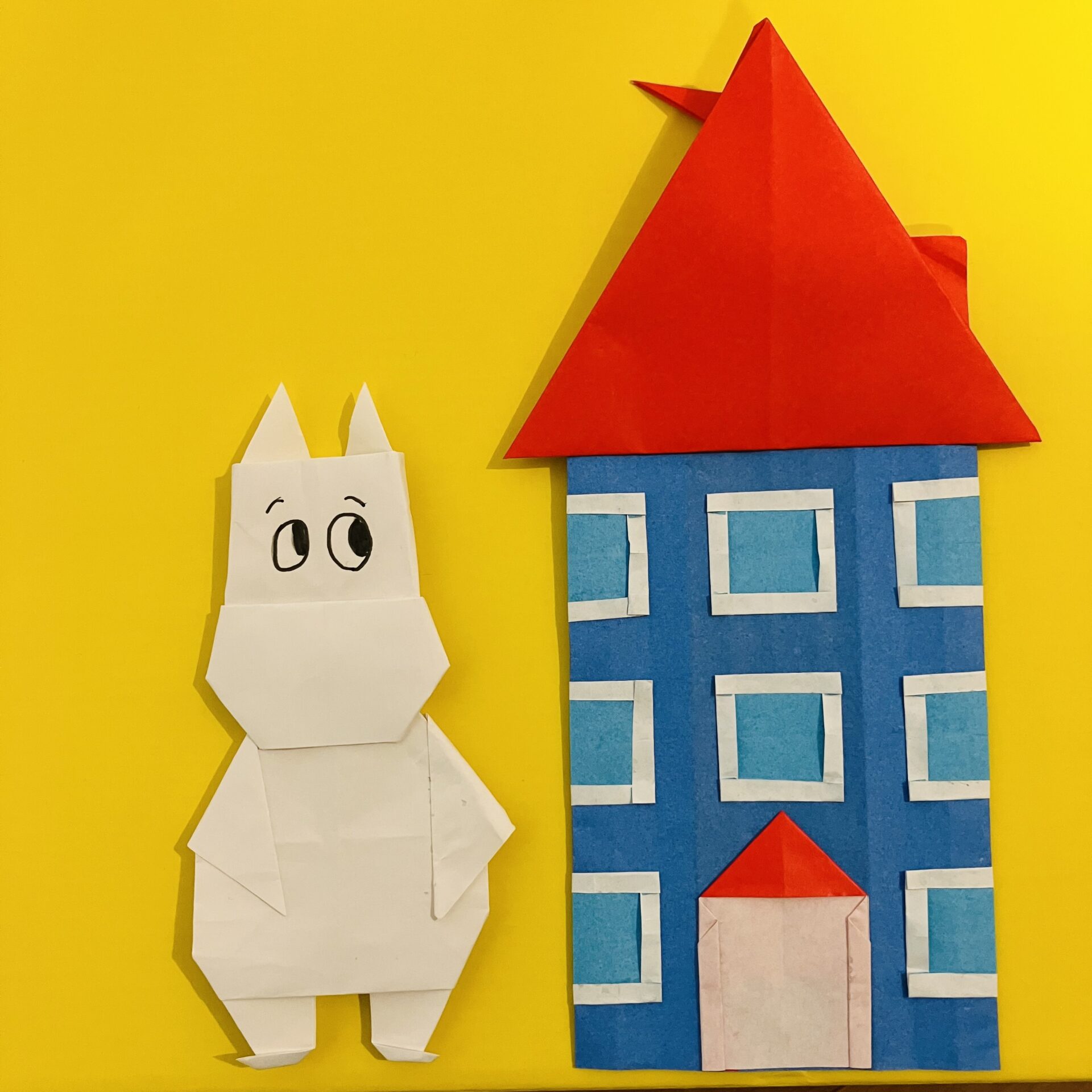これまでも「5歳児健診」を実施していた自治体はありましたが、2024年頃より「5歳児健診」を実施、または実施を検討する自治体が増えてきています。
なぜ今「5歳児健診」を実施する自治体が増えてきているのでしょうか?
その背景について、まとめました。
※2025年(令和7年)2月15日現在
「5歳児健診」とは何か
こども家庭庁による「5歳児健診」の説明より
- 主な目的
幼児の言語理解能力や社会性が高まる時期である5歳児に対して健康診査を行い、発達障害等のこどもの特性を早期に把握し、こどもとその家族を必要な支援に繋げること。 - 対象
原則として4歳6か月から5歳6か月の幼児 - 内容
「身体発育状況」「栄養状態」「精神発達の状況」「言語障害の有無」「育児上問題となる事項の確認」「その他の疾病及び異常の有無」の6項目
「5歳児健診」が増えてきた理由
「5歳児健診」に関する最近の国の動き
| 2023年 10月 | 公費負担する乳幼児健診について、5歳児も対象とする方向で調整開始 |
| 2023年 11月 | 2023年度補正予算に、5歳児健診の実施に必要な経費が計上 |
| 2023年 12月 | 法的根拠が明確化(こども家庭庁から各自治体宛てに5歳児健診の実施に関する通知が出された) |
| 2024年 1月 | 5歳児健診を実施する自治体への国の助成事業開始 |
| 2024年 5月 | 『こどもまんなか実行計画2024』において「5歳児の健康診査の実施に係る支援を進め、全国展開を目指す」ことが明示 |

これらの流れを受けて、全国の各自治体で「5歳児健診」を実施する基盤が整ってきたため、2024年頃から「5歳児健診」を実施する自治体が増えてきています。
尚、2025年2月現在、母子保健法において「5歳児健診」は、自治体の判断で実施される任意の健診とされています。
こども家庭庁は、国が財政支援をすることで各自治体に「5歳児健診」を推奨し、令和10年度を目標に全国での展開を目指していますが、現在のところ、母子保健法においては、1歳6か月児健診と3歳児健診のように義務化はされていない状況です。

義務化はされていませんが、国が政策として推し進めているため、急スピードで全国展開されていくことが予想されます。
これまでも実施していた自治体があるのはなぜ?
これまでも、全国の15%の自治体が「5歳児健診」を実施していました(令和3年に厚生労働省が発表した母子保健事業の実施状況の報告)。
母子保健法の第十三条には「前条の健康診査(義務化されている健診)のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。」と定められています。
これに基づいて、各自治体の判断で「5歳児健診」が実施されていました。

母子保健法に基づき「5歳児健診」を実施することは可能ですが、義務化はされておらず、国からの財政支援もなかったため、実施している自治体としていない自治体とがありました。